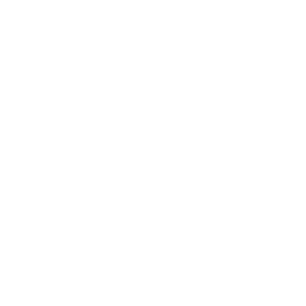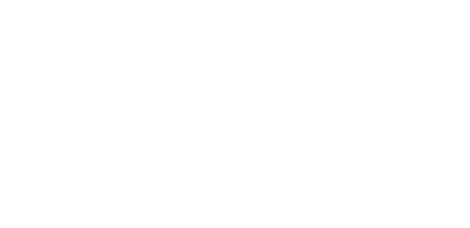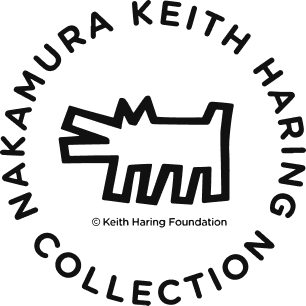ニュース
NEWS
当館では10月13日、鑑賞ワークショップ「キース・ヘリングにふれてみよう」を開催しました。本日はその様子をご紹介します。
本ワークショップは、世界視力デー(毎年10月の第2木曜日)にあわせ、「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ(愛称:とつくる)」のご協力のもと実施したものです。
目の見える人、見えない人、見えにくい人が一緒になって、さまざまな方法でキース・ヘリングの作品や思想にふれることを目的とした鑑賞プログラムです。
現在当館では、今年新たに収蔵した全長5メートルを超える彫刻《無題(アーチ状の黄色いフィギュア)》を記念し、ヘリングの彫刻作品に焦点を当てた展覧会「Keith Haring: Arching Lines 人をつなぐアーチ」を開催中です。
ヘリング自身は、鑑賞者が実際に“触れることのできるアート”として彫刻を制作していましたが、当館では作品の保存と継承の観点から、通常は来館者が作品に触れることをご遠慮いただいています。「触れられることを前提に生まれた作品」と「触れることを制限せざるを得ない現実」との間にあるジレンマから、今回のワークショップは企画されました。
ワークショップの冒頭では、「さわる」と「ふれる」という言葉の違いに注目しながら、参加者同士で意見を交わしました。伊藤亜紗さんの著作『手の倫理』では哲学者の坂部恵さんの言葉として「さわる」と「ふれる」をこんなふうに紹介しています。
「さわる」は一方的な行為であり主に“もの”との関わりで用いられる、一方、「ふれる」は相互的な行為であり、“ひと”など生きた存在との関わりで用いられる。
それではキース・ヘリングの彫刻作品を手で鑑賞する時、それは「さわる」なのか「ふれる」なのか、そんな問いを参加者の皆さんと共有しながら鑑賞ツアーが始まりました。
鑑賞ツアーでは、ナビゲーターの案内のもと、まずは絵画作品から鑑賞をスタート。ヘリングの作品の特徴やこの作品がもつ独特な色彩や造形について意見が飛び交いました。

続く彫刻作品の鑑賞では、「目で見る見る」ことと「手で触れて見る」ことの違いを体感。
参加者はアクセサリーを外し、手袋を装着して作品に触れてみました。視覚だけでは得られない形や質感の情報を手で感じ取り、ヘリング作品への新たな理解が生まれました。

最後には、現在開催中の展覧会「Keith Haring: Arching Lines 人をつなぐアーチ」のハイライトであり、今年新たに当館のコレクションに加わった《無題(アーチ状の黄色いフィギュア)》を鑑賞。遠くから全体を眺めたときと、近くで実際に触れたときの印象の違いを感じたり、作品のプロポーションやスケールの緻密さに驚く声もあがりました。


参加者の皆さま、そしてナビゲーターとしてご協力くださった「とつくる」の林さん、松本さん、誠にありがとうございました。